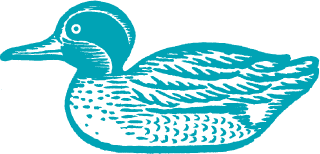5月1日(日)の昼下がり、いせひでこさん をお迎えして、ギャラリートークが開催されました。
絵本『たぬき』は、2011年の春、東日本大震災の後にいせひでこさんの家の庭に現れたたぬきの一家のお話です。「皆さんはこの10年をどのように過ごされましたか? 皆さんのこの10年を振り返りながらお聞きください。」という言葉で始まりました。

2011年3月11日の東日本大震災の後、預かっていた初孫の6ヶ月の赤ちゃんが4時間も泣き続けたり、無傷のカラスが死んでいたりしていて、何かが変わってしまったと感じました。そして、それは絵本『たぬき』の冒頭の言葉になっています。
あの日から、風がかわった。
空気がかわった。光がかわった。
思ってもみなかった日常が出現した。 (本文より)
いせさんは震災の日から、地震の記録、原発事故の報道などを小さなメモに記していきました。
4月、自宅の庭にたぬきが出現しているらしいことに気づきました。その後、朝、デッキの上のスリッパが動いているのにも気づき、6月、デッキの人感センサーの明かりにたぬきの子と親が浮かび上がったのです。6月以降、「地震日記」は「たぬ記」という観察日記になっていきました。
また、震災直後、何ができるのだろう、「生きる」って何なんだろうと考え、未来に向かって生きてほしいという気持ちで、植物の種の芽吹きにいのちを託した『木のあかちゃんズ』(平凡社)を7月に刊行し、被災地の飯館村の子どもたちに届けました。子どもたちとの交流は今も続いています。
「たぬ記」にも、マヨネーズ事件、月夜の踊り、母さんたぬきの事故、4日間続いた祈りの儀式、父さんたぬきの失踪、長女の子育て、旅立ち…たぬきたちのいのちの営みが描き記されていきました。
実際の「たぬ記」のコピーを見せていただきながら、お話を聞きました。
「生きる」を示してくれたたぬきたち、たぬきは「生きるエネルギー」そのものでした。
震災後、毎年3月には被災地を歩いてきたいせひでこさん 、10年後の2021年3月11日、被災地から帰ると無条件に「生きる」を描きたいと思ったそうです。「生きる」って何なんだろうと思って描き始めたのが「たぬき」だった、“いのちのかたまり” だと思った、「たぬき」なら描けると思ったそうです。そして、絵本『たぬき』が誕生しました。
いせさんは、月刊の俳句誌「岳」の表紙を、上半期、下半期の年2回描いているのですが、そこにも「たぬき」が登場(2021.7~12)。「岳」の表紙には、いせさんの心の軌跡を表すような絵、時には絵本の主人公たちも登場しています。
「岳」の表紙の拡大コピーを見せていただきました。
俳句や短歌のお話も心にしみました。
『見えない蝶をさがして』(平凡社)『わたしの木、こころの木』(平凡社)にもたぬきの親子が登場しています。ぜひ、探してみてくださいね。
サイン会も、大盛況!
この日のためにいせさんが摘んできてくださった「ハハコグサ」(春の七草のゴギョウ)「スズメノヤリ」。「母子草」がたぬきの親子にやさしく寄り添います。
母子草を手に記念撮影
そして、何と豪華な記念撮影が!
左から『あの路』の山本けんぞうさん、『あまがえるのかくれんぼ』のかわしまはるこさん、『がろあむし』の舘野鴻さん、いせひでこさん、『ねえ、しってる?』のかさいしんぺい さん
親をなくしたたぬきの子らが「生きる」ために西へ西へと旅立ったように、私たちもこの不穏な時代を生き抜かなくてはと思いました。そして、いせひでこさん が苦しみながらも「生きる」を描こうとする姿に勇気をもらいました。
いせさんの冒頭の言葉の通り、お話を聞きながらそれぞれがこの10年に想いを馳せたことでしょう。心にしみるギャラリートークでした。
いせひでこさん 、平凡社の三沢秀次さん、ありがとうございました。
参加くださった皆さん、ありがとうございました。
『たぬき』原画展は、5月29日(日)まで。
【いせひでこさん の在廊日】
5月15日(日)、5月29日(日)、いずれも14時〜17時まで。
皆様のお越しをお待ちしています。