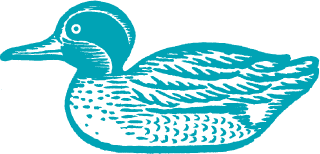4月20日(土)第71回コガモ句会
4月20日(土)の夜、俳人の土肥あき子さんをお迎えして第71回コガモ句会が開催いたしました。

兼題は【蝶】
紋白蝶や蜆蝶など身の回りに見る蝶でも、春になってその年初めて見かける初蝶でも、蝶の舞う春らしい景色を詠んでみましょう(土肥あき子さんより)
高点句は、
初蝶やハミングの出る厨事 幸江
野良仕事腰を伸ばせば初蝶来 悦子
花びらの流れてふいに蝶となる 有希
この日の席題は【春の風邪】
あたたかくなったと油断した時にひいてしまう風邪。病気ではあるが、春という季節が独特のユーモアも陰影も持たせる。(土肥あき子さんより)
高点句は、
春の風邪そっと扉の開く音 のりこ
コロナさえ寄りつかぬ吾に春の風邪 久美子
春の風邪熱持つ頰のうつくしき 有希
老医師の書き込むカルテ春の風邪 顕人
春の風邪熱はからずに仕事場へ 登水子
始まりはくしゃみ十回春の風邪 節子
この季節、実感を持って詠むことができたのでしょうか。共感できる句が多く、点が割れました。
次回のコガモ句会は、2024年6月8日(土)18:00〜19:30です。
兼題は、【水馬】あめんぼう・あめんぼ
コガモの投句も受け付けています。「当季雑詠」、その季節の句であれば何でも大丈夫です。締め切りは2024年6月8日(土)、直接お持ちいただくか、FAXまたは郵送でお願いいたします。
季節の移ろいを感じながら、日々の暮らしを彩る俳句。皆さんと一緒に楽しんでみませんか。ご参加をお待ちしています。
4月13日(土)なかがわちひろ さん・高橋和枝さん ギャラリートーク&サイン会
4月13日(土)、気持ちのよい春の陽気の中、『とってもすてきなおうちです』(アリス館)の作者 なかがわちひろさん、高橋和枝さん、装丁家の中嶋香織さん、アリス館編集者の山口郁子さんをお迎えして、ギャラリートーク&サイン会を開催いたしました。
まずは、この絵本の始まりのお話から。
10年ほど前に、編集者の山口郁子さんとなかがわちひろ さんとの間で「人間と生きものが気持ちよく暮らすおうちが素敵!」「人間だけでなく、生きものたちにとっても大切な“ ここがおうち” といえるようなおうち」を絵本の形で表現できないかと話されたそうです。テキストはなかがわさんが書き、絵は他の画家さんに。「絵本は絵描きのものだけど、テキストは骨」とおっしゃるなかがわさん。

その後、「気持ちのよい風が描ける人」を探したところ・・・高橋和枝さんに白羽の矢が!

高橋和枝さんとは、 なかがわさんは6年ほど前に出会っていました。当時連載されていた漫画の『火曜日のくまこさん』(中央公論新社)の読み、穏やかでやわらかい雰囲気の和枝さんですが、芯がビシッとしているんだなと思ったそうです。『うちのねこ』(アリス館)にも注目したそうですよ。
2021年7月に、絵を描くことに決まった和枝さんでしたが、それまで虫に興味を持ったことがほとんどなかったので描けるのか不安だったそうです。なんと、この絵本にはたくさんの虫や生きものが登場するのです。
それから、アリやツバメやクモの観察に励み・・・「アリの巣観察キット」で見たアリたちをかわいい!って思えるようになりました。
その後、なかがわさんから青虫のついたキャベツが全員に送られてきて、それぞれ観察し育てました。さなぎから蝶々に羽化するまでにも様々なエピソードがあったようです。
今回の絵は、和紙に水彩絵の具や墨などで描いているのですが、全体に柔らかい光を感じるのには秘密が!
なんと、紅茶を画材として使われたそうです。和枝さんがアリの土の色やはちみつ色のひなたなど、どう描くか悩んでいたところ、偶然、なかがわさんからイギリスには紅茶で絵を描いている作家さんがいることを教えてくれたそうです。以心伝心ですね。
画家は、いろんな画材や画法を試みながら、より良い作品を描こうとするのですね。
デザイナーの中嶋香織さんも、今回の絵本では初めからチームに加わり、表紙をはじめ絵本として一番良い形で送り出してくれました。印刷の際にも一緒にチェックしたそうです。中嶋さんによる帯のデザインも素敵です。ぜひチェックしてみてくださいね。

最後に、お二人で『とってもすてきなおうちです』を読んでくださいました。
質問のコーナーでも、「絵本を作るにあたって一番大切にしていることは?」など鋭い質問もでて、みなさん真剣に答えてくださいました。
作家、画家、装丁家、編集者、お互いをリスペクトし合う4人のチームワークの良さが作品に表れていることがよくわかりました。

談笑しながらのサイン会

高橋和枝さんとなかがわちひろさん、素敵な笑顔です😀
お二人の洋服にも注目! 絵本に登場する青虫? 菜の花? キャベツ? 会場は春色に染まりました。
絵本のタネが生まれてから10年、たくさんの生きものの観察にも時間をかけて丁寧に創られた作品であることがよくわかりました。人間以外にもいっしょに生きていく命があることを子どもたちとおおらかな気持ちで楽しみたいですね。
なかがわちひろ さん、高橋和枝さん、中嶋香織さん、山口郁子さん、アリス館さん、ありがとうございました。
参加くださった皆さんも、ありがとうございました。
原画展は、4月28日(日)まで。お待ちしています!
3月28日(木)なかがわちひろ・文 高橋和枝・絵『とってもすてきなおうちです』絵本原画展が始まりました。

なかがわちひろ/文 高橋和枝/絵 アリス館 定価1,650円
うららかな春の日の3月28日(木)、高橋和枝さんの『とってもすてきなおうちです』(なかがわちひろ/文 アリアス館)の絵本原画展が始まりました。
ティールームは、春の陽射しを感じるような暖かさに包まれています。

高橋和枝さんの透明感あふれる水彩画があたたかく心にしみ込みます。

暖かな陽射し、土の匂い、花の香り、猫の毛並み‥‥五感を通して春を感じます。 

気持ちよさそう〜
小さな生きものたちにとって居心地の良い家なら、人にとってもやさしい居心地の良い家なのですね。

『とってもすてきなおうちです』は全てなかがわちひろさん、高橋和枝さんお二人のダブルサイン本です。『うちのねこ』『月夜とめがね』『あめのひのくまちゃん』など、高橋和枝さんの著作本もいっぱい並んでいます。

こちらは、なかがわちひろさんの著作本のコーナー。『天使のかいかた』『ハンカチともだち』『やまの動物病院』『とらまる、山へいく』『すてきなひとりぼっち』『ぼくは、ういてる』など、ロングセラーから最新刊の本まで並んでいます。

この絵本が出来上がるまでの「制作のゆるゆる記」も必見! 蝶々が羽化するまでの観察記や家の周りの観察記など、手書きの文字なので高橋和枝さんが語りかけているようです。
高橋和枝さんが今回の展示のために描き下ろしてくださった額絵も展示販売しています。ポストカードも! どれも素敵ですよ✨
【高橋和枝さん在廊日】
4/5(金)、4/18(木)、4/20(土)、4/28(日)いずれも14:00〜17:00
【トークイベント・サイン会】
4/13(土) 14:00〜15:00 (予約者のみ・満員御礼)
15:45〜サイン会はどなたでも参加できます。
原画展は、4月28日(日)まで。
皆様のお越しをお待ちしています🦆
3月24日(日)さとうゆうすけさん原画展 終了しました。
3月24日(日)、さとうゆうすけさんの『夜の妖精フローリー』『小学館世界J文学館 グリム昔話集[初版]』の原画展が終了いたしました。
最終日の11時から14時まで、さとうさんが在廊してくださり、駆けつけてくださった方たちと作品が出来上がるまでの舞台裏のお話をしてくださいました。
例えば・・・

羽をもがれたフローリーは、巨人(ニンゲン)の庭に落ちてしまいます。翌日目にした昼間の世界は、ちぎれたつばさの痛みも忘れるほどの美しさで、フローリーは昼の妖精になる決心をします。

そんな重要なシーンの挿絵ですが、フローリーが見た光景を描くために巨人(ニンゲン)の庭も具体的にイメージして描くなど、物語を深く読み込み、その世界を緻密に創り上げていることがよくわかりました。
アライグマの表情は、作者のローラ・エイミー・シュリッツさんも納得してくださったとのことですよ。
アメリカでもともとアンジェラ・バレットさんの挿絵で出版されていた『The Night Fairy』の日本語版なので、作品の隅々までさとうさんの熱量が伝わってきました。
どのお話も興味深くあっという間の3時間でした。
実は、今年の12月に、さとうゆうすけさんの『こねこのウィンクルとクリスマスツリー』(ルース・エインズワース/さく 上條由美子/訳 福音館書店)の原画展を開催予定です。



表情豊かなこねこのサインが素敵です。
さとうゆうすけさんの繊細で美しい絵でエインズワースの世界を味わうことができることを嬉しく思います。どうぞお楽しみに!
さとうゆうすけさん、Gakkenさん、小学館さん、そしてお越し下さった皆さん、ありがとうございました。
3月7日(木)さとうゆうすけさん原画展 〜『夜の妖精フローリー』『小学館世界J文学館 グリム昔話集[初版]』〜
3月7日(木)、さとうゆうすけさんの『夜の妖精フローリー』(Gakken)『小学館世界J文学館 グリム昔話集[初版]』の原画展が始まりました。

ローラ・エイミー・シュリッツ/作 日当陽子/訳 さとうゆうすけ/絵 Gakken
 ヤーコブ・グリム、ヴィルヘルム・グリム 吉原高志、吉原素子/訳 さとうゆうすけ/絵 小学館
ヤーコブ・グリム、ヴィルヘルム・グリム 吉原高志、吉原素子/訳 さとうゆうすけ/絵 小学館

繊細で美しいさとうさんの原画が、並んでいます。

原画ならでは発見もありますよ!
作品にちなんだモビールが楽しそうに揺れています。(販売しています)

グリム昔話集の原画も見応えがあります。
『夜の妖精フローリー』『こねこのウィンクルとクリスマスツリー』(福音館書店)はこだわりのサイン入りです。フローリー、スカッグル、こねこのウィンクル、可愛いですよ💖
『ノロウェイ の黒牛』(BL出版)には、サイン入りカードが入っています💕

『夜の妖精フローリー』ができるまでの制作ファイルは、たくさんのラフを見ることができます。フローリーのサイズや巨人(ニンゲン)の庭の見取り図など注目です!
心血を注がれた作品であることがよくわかります。
今回、額絵も展示販売しています。
「スノードロップ」「キノコ」「花輪」どれも素敵な妖精たちを描き下ろしてくださいました。

原画展のDM
ある晩、美しい羽をもがれ、巨人(ニンゲン)の庭に落ちた夜の妖精フローリー。
悲しみの中、目にした昼間の世界は胸がドキドキするほど美しいものでした。
「いまから、わたしは昼の妖精になるわ」
まっすぐな心で、世界を生きぬき、自分の居場所を見つける妖精の物語を、さとうゆうすけさんの繊細で美しい原画でお楽しみください。
原画展は、3月24日(日)まで。
さとうさんの在廊日が決まりましたら、お知らせいたします。
3月3日(日)「ぴよちゃん えほん」原画展、終了いたしました。
世界中の子どもたちに愛されてきたいりやまさとしさんの「ぴよちゃん」シリーズ(Gakken)の原画展、3月3日(日)に無事に終了いたしました。
最終日も、たくさんの親子連れで賑わいました。

「懐かしい〜」と言って、原画の前で思わず声が出た中学生の女の子。小さい時になんども読んでもらったのでしょうね。

似顔絵入りのサインに、皆さん大喜び💖

いりやまさんは、地元の作家さんなので、たびたび自転車で駆けつけ在廊してくださいました。
時には、ギターの演奏をしてくださったり、ウクレレを弾いてくださったり、和やかな時間が流れていました。優しく温かいぴよちゃんの世界そのままでした。
20年間シリーズで皆さんに愛され続けている絵本、すごいことだと思います。これからも子どもたちにとって友だちのような存在の絵本でありますように!
いりやまさとしさん 、Gakkenさん、お越し下さった皆さん、ありがとうございました。
2月10日(土)第70回コガモ句会
2月10日(土)の夜、俳人の土肥あき子さんをお迎えして、第70回コガモ句会が開催されました。

兼題は【薄氷】
ごく薄く張り、昼頃には解けてしまう氷のこと。2月は寒さ極まる頃だが、暦の上では立春を過ぎれば春なので、積極的に春めいたものを探して一句を詠んでみましょう。(土肥あき子さんより)
高点句は、
薄氷に捕らわれている木の葉かな 有希
薄氷の端から水になりたがる あき子
薄氷や番の鳥の煌めきて 千枝子
薄氷のかざして見れば陽の涙 末子
この日の席題は【余寒】
二月の気温は一年で最も低い。それでも立春後の寒さということで「余分」の「余」が使われる。語幹の鋭さも印象的。厳しい寒さであっても、もうすぐ春らしい陽気になることの確信もある。(土肥あき子さんの資料より)
高点句は、
ファスナーの噛みつく服に余寒あり 幸江
皿に皿重ね合はせる余寒かな 千枝子
約束を延ばしては待つ余寒かな 花美
この季節にぴったりの季語。思いもかけない瞬間なのですが、なるほどと共感の声が上がりました。
次回のコガモ句会は、2024年4月20日(土)18:00〜19:30です。
兼題は、【蝶】蝶々、紋白蝶、初蝶
コガモの投句も受け付けています。「当季雑詠」、その季節の句であれば何でも大丈夫です。締め切りは2024年4月20日(土)、直接お持ちいただくか、FAXまたは郵送でお願いいたします。
季節の移ろいを感じながら、日々の暮らしを彩る俳句。皆さんと一緒に楽しんでみませんか。ご参加をお待ちしています。
2月10日(土)いりやま さとしさん スペシャルイベント
2月10日(土)の午後、「ぴよちゃんえほん」シリーズの作者いりやま さとしさんをお迎えして、スペシャルイベントが開催されました。
赤ちゃんから大人まで、たくさんの方が参加くださいました。すると・・・

なんと! 動くぴよちゃんが登場したのです🐥 小さいお子さんはびっくり!
そして、うごくしかけ絵本『まねっこ おかお』をいりやまさんのギターの伴奏に合わせてみんなで歌いながら楽しみました♪


この日のために駆けつけてくださったお姉さんたち、みなさんの前で歌ってくれました。
次に、いりやまさんがぴよちゃんの絵をどのように描いているのかを実演してくださいました。

ステンシルの画法でパステルをたたいていきます。だんだん現れてくるぴよちゃんの姿に、「わぁ〜」と驚きの声が!

色鉛筆で目を描き・・・

ぴよちゃんの完成!
可愛らしいぴよちゃんは、このようにして生まれてくるのですね。
次は、ハートのフェルトにシールやビーズを貼ったり、クレヨンで絵を描いたりしてアクセサリーを作りました。



皆さん、どれも素敵✨
もうすぐバレンタインなので、大切な人への贈り物になりますね💖
最後は、ぴよちゃんと一緒にサイン会。


ぴよちゃんに四葉のクローバーを食べさせたり、記念撮影をしたりして楽しみました。
赤ちゃんの頃から親しんできたぴよちゃんを間近に感じながら、一緒に歌を歌ったり、工作をしたりして楽しいひとときを過ごしました。
いりやまさとしさん、Gakkenの皆さん、ありがとうございました。
参加くださった皆さんもありがとうございました。これからもぴよちゃんと仲良く遊んでくださいね🐥
2月8日(木)いりやま さとしさん「ぴよちゃん」原画展が始まりました。
2月8日(木)〜3月3日(日)まで、地元の絵本作家 いりやま さとしさんの「ぴよちゃん」原画展を開催いたします。
ティール・グリーンのティールームは、一気に春めいております。

世界中に愛されている「ぴよちゃん えほん」シリーズ(Gakken)。
2003年に誕生して昨年2023年に20周年を迎えました。昨年から20周年を記念した原画展が各地で解されていましたが、今回、作者のいりやまさとしさん の地元の当店で原画展をさせていただきます。『ぴよちゃんの おともだち』を中心に原画を展示しています。

いりやまさとし/さく・え Gakken

「ぴよちゃんえほん」シリーズは、やさしいパステルタッチの絵が人気のファーストブックです。
開店直後にいらした親子連れさんも「おうちにある絵本だね〜」と2歳くらいの女の子に声かけながら原画を楽しんでいらっしゃいました。幼いお子さんたちにとっては馴染みの深い絵本、キャラクターなのですね。

記念すべき20周年に刊行された最新刊の『ぴよちゃんの おたんじょうび』の原画も展示されています。

ぴよちゃんと仲良しのかるがもの女の子ガーコちゃん。

「ぴよちゃんえほん」シリーズの絵本がたくさん並んでいます。お気に入りの絵本に出会えるといいですね💖
好奇心旺盛で純真無垢なひよこの「ぴよちゃん」は小さな子どもそのもの。ぴよちゃんがともだちと出会ったり、迷子になったり、妹ができたり・・・などと実際の暮らしの中で体験することをやさしくやわらかい絵で描いています。子どもたちも共感しながらぴよちゃんの世界に入っていくのでしょう。だからこそ、20年間にわたり皆さんに愛されているのですね。
丁寧に描かれた原画を見ているといりやまさんの誠実さ、温かさが伝わってきます。ぜひ間近でご覧になってくださいね。
皆様のお越しをお待ちしています🦆💕
*2月10日(土)のいりやま さとしさんのスペシャルイベントは定員に達してしまいましたが、15時からのサイン会はどなたでも大歓迎です! お待ちしています!
2月4日(日)想造工房展、終了いたしました。
想造工房さんの「どんなかな、こんなかな木工展」、好評のため会期を延長しましたが、2月4日(日)に終了いたしました。
今年もたくさんの方に喜んでいただきました。時計や、オーナメント、モビール、ハンペルマンなど木工展ならではの作品をそれぞれの家に迎えていただき、嬉しいことでした。

ハンペルマンの子ぎつねは赤い手ぶくろを買ったので、元気よくお家に帰りました。

桃のお節句のお雛様はもう少しティール・グリーンで、皆様をお迎えしてくれます。
たくさんの素敵な作品を揃えてくださった想造工房の奥田守保さん、オクダチズさん、ありがとうございました。
お越し下さった皆さん、ありがとうございました。